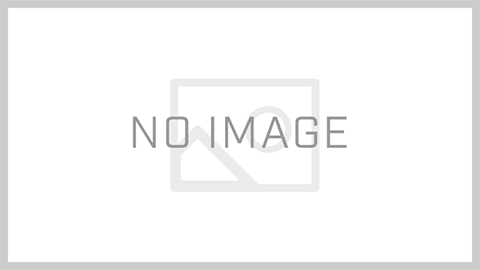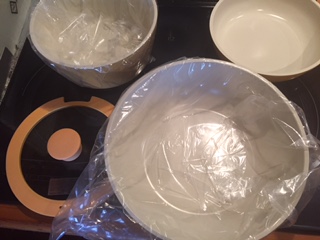先週から、漢方薬をのみはじめました。
いろいろ書籍や専門家のYouTubeをみて、
(西洋医学を否定するつもりはないです)
漢方の力で体質改善ができたらいいなということで。
ちなみに、病院からのお薬を飲みながら、漢方薬を飲むことは可能なのか?
という、疑問というか不安があったのですが、私の漢方の先生は「飲む時間を
ずらせば、どちらも飲んで構わない」とおっしゃいました。
だけど、西洋医学の先生は併用して飲むことを嫌がる先生もいるそうです。
確かに私は「自己責任」と言われました。そう言ってくださる先生はマシ?なんだそうです。
Contents
西洋医学の薬と漢方薬のアプローチの違い
西洋医学のお薬は炎症や痛みという症状に直接作用するようになっています。
漢方薬は、血の巡りをよくしたり、体内の免疫力をあげるなどして、体質を改善していきます。だからこそ、西洋医学のお薬が効くようにもなるのだそうで、この二つは併用可能ということです。
漢方薬のカウンセリングと処方の仕方
漢方薬は「証(しょう)」症状パターンに基づいて処方されます。
証とは?
漢方では証(しょう)を特定する3つの要素は「気・血・水(き・けつ・すい)」となります。
気:体を動かすエネルギーで、不足すると気力がなく倦怠感が現れやすい
血:体内の血液の状態
水:体内の水分の状態
漢方では、この3つの要素の状態によって「虚証(不足している状態)」と「実証(めぐりが悪い状態)」に分けられます。これらはその時々で状態は変っています。
漢方の問診は西洋医学の問診とは違った(アンケートに記述するなど)
悩んでいる病気や症状について
便やおしっこについて、体の冷えについてなど、体についてはもちろん
何を最初に治したいのか?
今後どうありたいのか?など、心理カウンセリング?コーチング?
と感じるような質問もあったのですよ。
漢方では、一人ひとりの病態だけでなく、体質を重んじて漢方薬が処方されます。
そのため、ときには治してもらいたい病気や症状とは関係のなさそうな、
違う症状に効くと言われている漢方薬が処方されたりします。
そのため、一つの漢方薬が複数の症状に同時に作用することが特徴です。これは、西洋医学の「病名」に対するアプローチとは異なり、「体全体のバランスを整える」ことを目的としているからです。
体質(証)を整えることで、複数の症状を改善
例えば、「血の巡りが悪い(瘀血=おけつ)」体質の人は、このような症状で悩んでいると思います。
●冷え性(血流が悪いため手足が冷える)
●肩こり(血液が滞り筋肉が硬くなる)
●生理痛(血流が悪いため経血の排出がスムーズでない)
●シミ・くすみ(血流が滞ることで肌のターンオーバーのスピードが落ちる)
これらの症状に合わせて、漢方薬を処方してくださいます。ドラッグストアにも漢方薬が売られていますが、一人一人体質は違うので、専門家に証を診てもらい自分にあったお薬を調合してもらうのがいいです。自己判断で漢方薬を飲むのはやめましょう。
例えばウコンは、お酒を飲む方が肝臓の数値が悪い場合はいいのですが肝障害がある人では漢方薬では違うお薬を処方することがあるそうです。
私も思っていたものとはまったく違う初耳な漢方薬が処方され
帰宅してネットで効能を調べてみて「へえ、そうなんだ」的に納得して飲んでいます。
いわゆるオーダーメイドのお薬処方になるわけです。
即効性のある西洋医学のお薬とは違って、漢方薬は速効性はなく効果を感じるまでに時間がかかるそうで、合わない漢方薬を飲んで「効かない」とすぐにやめてしまわれる方が多いそうです。
漢方薬はお金がかかるので、長く続かない人もいるそうです。
なんでも時間をかけないほうが「時短」ともてはやされる時代なので
ゆるやかに効く漢方薬を頑張ってみようと思っている私です。
こんな「時長」が今の自分には必要なのかも・・と。