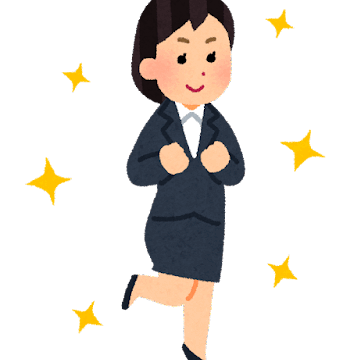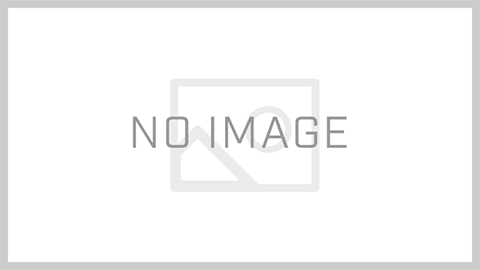言葉の力で病気をやめさせる心理技術アドバイサー、神経科学研究家の
梯谷幸司さんによると、
病気になると、生活習慣が悪かったからとか
遺伝だからとか思ってしまうけど、
あまり関係ないと
動画でおっしゃっていました。
「脳」の動かし方を間違うと
病気になりやすい体になる、病気が続くと
いうことです。
でも、ストレスも多少は関係しているはずですよね。
ストレスとセロトニンの関係:心を整える「幸せホルモン」の秘密
私たちが日々の生活で感じる「ストレス」。学校や仕事、人間関係などで避けられないものですが、心と体の健康に大きく関わっています。
そのカギとなる「セロトニン」という脳内物質があります。
セロトニンとは?
セロトニンは、別名「幸せホルモン」とも呼ばれる神経伝達物質です。
脳や腸に多く存在し、次のような役割を担っています。
気分を安定させる
睡眠のリズムを整える
食欲を調整する
自律神経のバランスを保つ
だからセロトニンは、心を落ち着けたり安心感を生み出す働きがあり、私たちの「心の土台」を支えているのです。
ストレスとセロトニンの関係
強いストレスを受けると、体は「戦うか逃げるか」という緊張状態に入り、交感神経が優位になります。
このときセロトニンの働きは弱まり、気分が不安定になったり、心が疲れやすくなったりします。
さらに、慢性的にストレスを抱えるとセロトニン不足が続き、次のような不調につながります。
イライラしやすい
気分の落ち込みやうつ症状
眠りが浅い、寝つきが悪い
集中力や意欲の低下
下痢、便秘、頭痛や肩こりなど体の不調
まさに「ストレス → セロトニン不足 → 心身の不調」という悪循環が生まれてしまうのです。
病気とは体の中の不調、不具合が症状として
現われる「体からのお知らせ」。
病気はつらいものだけど、
そういえば最近寝てなかった
そういえば悩んでいたことがある
そういえば顔も見なくない人がいる
とか、心身共に疲れていたなと
気づくことがありますよね。
結局、ストレスをうまく処理できていなかった
自分の心=脳をうまく調整できていなかったってことですね。
幸せホルモンのセロトニンを
増やすことを心がけるのも大事だと思います。
セロトニンを増やすための生活習慣
大切なのは、セロトニンを「自然に増やす習慣」を日常に取り入れることです。
食事でセロトニンを増やすには
◆大豆製品、乳製品、魚、バナナなどに「トリプトファン」というセロトニンの材料になる
必須アミノ酸が含まれています。これは体内では生成されないので、食事で取り入れるといいです。
またトリプトファンは、安眠を促すメラトニンの材料にもなります。
◆運動で活性化
ウォーキングやジョギング、サイクリングなどリズムのある運動が効果的です。
日光を浴びる
朝に太陽の光を浴びると体内時計がリセットされ、セロトニンが活性化します。
規則正しい睡眠
決まった時間に寝て起きる習慣が、セロトニンの安定につながります。
リラックス法を取り入れる
まとめ
セロトニンは、ストレスと深く関わる「心の安定剤」のような存在です。
ストレスをゼロにすることはできませんが、生活習慣を整えることでセロトニンを味方にし、心身を健やかに保つことができます。
今日からできる小さな工夫――例えば「朝の散歩」や「バナナを食べる」ことからでも、セロトニンを増やす第一歩になりますよ。
生活習慣や食事も気をつけたいです。